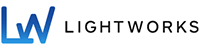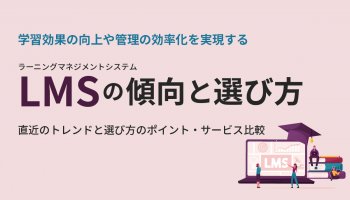日本の雇用は歴史的な転換点にある
働き方の変化に対応できる人材開発をICTでサポート
株式会社ライトワークス 代表取締役社長
江口 夏郎さん

現在、多くの企業が人材開発に注力し、従業員がキャリアを意識しながら自律的に学べる環境の整備に取り組んでいます。そうした企業の力強いパートナーとなっているのが、ラーニング・マネジメント・システム(LMS)の「CAREERSHIP」です。同サービスを開発・提供している株式会社ライトワークスの創業メンバーであり、代表取締役社長の江口夏郎さんに、起業のきっかけ、LMSを主力事業とした経緯、現在の日本企業の「人・組織」にまつわる課題、さらには同社の今後の展望まで幅広くうかがいました。
- 江口 夏郎さん
- 株式会社ライトワークス 代表取締役社長
えぐち・なつお/1991年に農林水産省に入省。株式会社グロービスを経て、2001年に株式会社ライトワークスに参画。2002年に株式会社ライトワークスの代表取締役に就任。
米国留学で出合った「起業」という選択肢
創業されるまでのキャリアをお聞かせください。学生時代はどんな分野を学ばれていたのでしょうか。
学部は理工系で、AI、特に今でいう機械学習を研究していました。年中コンピューターに触れている学生生活でしたね。今でこそAIの進歩には目をみはるものがありますが、1980年代はまだオモチャのようなレベル。苦労が多いわりにできることには限界がありました。そこで大学院に進む際に、以前から興味があった経済学の分野に転じることにしました。
専攻したのは労働経済学。テーマは「労働供給曲線のバックワードベンディング」です。一般の方にはあまりなじみがないかもしれませんが、いわゆる「働き方の変化」に着目した研究です。人間は給与が上がると、より頑張って働くようになるのですが、収入が一定レベルを超えると逆に余暇を楽しむほうを優先してあまり働かなくなる、といったモデルの検証などを行っていました。コンピューターと労働経済の二つを勉強したことが、今の仕事につながっているように思います。
大学院修了後、農林水産省に入省されていますね。
大学院では大都市近郊の人たちの働き方を調べるために、三重県での現地調査を数多く行っていました。その縁で農水省ならそのまま研究を続けられることを知り、志望したんです。ただ、私の性格を知った農水省の人が「研究より行政のほうが向いている」と言ってくれたので、行政官として入省することになりました。
官僚としてスタートを切られたわけですが、その後キャリアチェンジして、貴社を創業されています。きっかけは何だったのでしょうか。
農水省には6年間在籍しましたが、転機になったのは米国イェール大学ビジネススクールへの留学でした。当時から中央官庁には国費留学の制度がありました。将来のキャリアをそこまで深く考えていたわけではないので、最初は「アメリカはどんなところだろう」という興味があっただけです。英語はある程度できたので手を挙げたところ、2年間の留学が許可されました。
渡米は1994年。ちょうどインターネットの勃興期でした。世界中で次々にWEBサイトが立ち上がっていて、アメリカに滞在していても、新聞社のサイトを見れば日本のニュースをリアルタイムで読めました。eメールも今ではあたりまえですが、当時は新鮮で驚きでした。そんな時代に世界中から人材が集まっていて、起業を考えている人もたくさんいました。同級生の間でも「卒業したら起業しようと思っている」といった話ばかり。大学側もインキュベーションセンターを用意して後押ししていました。大いに刺激を受けましたね。それまで起業など考えたことはありませんでしたし、農水省を辞める気もなかったのですが、いつしか自分も起業したいと強く思うようになっていました。
最初から具体的なビジネスのプランがあったわけではありません。ただ、これからの時代にインターネットは欠かせないと思っていました。大学院で「働き方」を研究し、日本でもこれから働き方が変わっていくことは予測していたので、漠然と「インターネットで働き方の変化をサポートするようなビジネスができないか」などと考えていましたね。

帰国して創業されるまでは、どんなことに取り組まれていたのでしょうか。
MBAを取得して1996年6月に日本に戻り、翌3月で農水省を退職しました。起業志向が固まっていたので、迷いはありませんでした。ただ、その時点では官僚の経験しかありません。まずはビジネスの現場を知る必要があると考え、経営に近いところで丁稚(でっち)奉公させてくれそうなベンチャー企業を探しました。そこで出合ったのがグロービスです。
当時のグロービスはまだ20人くらいの規模で、文字通りのベンチャーでした。入社時の肩書は執行役員でしたが、何でもやりました。最初はスクール事業の責任者。続いてeラーニング事業の立ち上げを任されました。今ではグロービスの中核ビジネスのひとつになっていますが、当時はそこまで大きくなるとは考えていませんでした。
ベンチャーなので、思いがけないトラブルや問題が毎日のように発生します。それらを経験したことで、自分が起業してから似たようなことが発生しても、冷静に対処できました。とても勉強になった時期でしたね。
2001年に貴社の創業に参画されます。どのような経緯だったのでしょうか。
グロービスの取引先だったアスキーが新しくeラーニング事業を立ち上げることになり、グロービスでeラーニングを手がけていた私に「一緒にやらないか」と声をかけてくれたのがきっかけです。当時のアスキーは財務状況が厳しく、新しい投資ができなくなっていました。そこでeラーニング事業を別会社にして、外部資本も入れて大きく伸ばすことになります。この構図を描いたのが、ライトワークス初代社長の松田辰夫さんでした。私も賛成だったので、グロービスにも話を通して出資してもらいました。他にNTT-X(現NTTコミュニケーションズ)の資本参加も決まり、株主3社による運営でスタートしました。
統合型LMS「CAREERSHIP」を開発
創業メンバーとしてライトワークスを立ち上げ、2002年からは代表取締役社長を務められています。実際に起業に関わってみて、どのような感想をお持ちになりましたか。
何もないところから起業したわけではなく、何社もの企業の出資を受けていたので、良くも悪くも株主に影響されることが多かったですね。まず、親会社だったアスキーが財政難に陥り、紆余(うよ)曲折のすえ、ライトワークスはアスキーを救済したCSK(現SCSK)の子会社になります。このタイミングでアスキー出身だった松田さんは退任し、私が新しく代表取締役社長になりました。また、グロービスが持っていた株式をCSKが引き取ることになったため、グロービスとの兼務を終えて、ライトワークスの経営に専念することにしました。
それでいったん落ち着いたのですが、今度はリーマンショックでCSKの経営が危うくなります。結果的にCSKは住商情報システムと経営統合して、現在のSCSKになるわけですが、その過程で子会社のライトワークスは整理の対象になってしまいました。会社を存続させるには自分たちで株式を買い取るしかありません。知り合いの企業に頼んで一部の株式を持ってもらったほか、私個人も銀行から、多いときは1億円前後の借り入れをしてライトワークスの株を買い増していきました。2022年に株式上場を果たすまで、そうした資本関連の苦労はありました。
ビジネス面ではどんな展開をされていたのでしょうか。
創業当初はアスキーが持っていたMS-Office関連の教育コンテンツを中心に、eラーニング事業を展開していました。それまでCD-ROMで販売していたコンテンツを企業向けにネットワーク経由で提供するビジネスです。その後もさまざまな教育コンテンツを増やしていきましたが、あたりはずれがあって売上はなかなか安定しません。しばらくはかなり苦しみました。
そのうち、顧客企業から「従業員の学習状況を管理するのに適切なツールはないか」と質問されるようになりました。そこで簡単なクラウドベースのLMS(ラーニング・マネジメント・システム)をつくって提供したところ、顧客から「こんな機能がほしい」「あれもできないか」と要望がどんどん出てきました。それに応えてバージョンアップを続けているうちに、「コンテンツよりもLMSのほうがビジネスとして可能性がある」と思うようになったのです。
これをきっかけに、徐々にLMSに軸足を移していくことになります。最初に次世代LMS「CAREERSHIP」をリリースしたのが2008年。さまざまな機能を持つ統合型システムとして現在提供しているeLMSの形になったのが2015年です。その前後から今につながる急激な成長がはじまりました。現在では大手企業を中心に1500社以上の顧客に導入していただき、クラウド型LMSの国内市場では売上シェアNo.1のサービスとなっています(富士キメラ総研「2023 SX/GXによって実現するサステナビリティ/ESG支援関連市場の現状と将来展望」学習管理システム(クラウド) 2022年度金額シェア)。
LMSに注力することは、江口社長がご自身で決断されたのですか。
学習コンテンツの提供は今も続けていて、すべてを切り替えたわけではありません。顧客の要望に応えているうちに、自然にLMSがメインになっていきました。また、当社のサービスはクラウドを使ったSaaS型で、当時としてはかなり先進的でした。SaaS型にしたのは、サーバー運営会社の提案にたまたま乗っただけで、新しい技術を意識したわけではありません。ただ、顧客からは「導入しやすい」と非常に評判が良かった。うまく時代の流れに乗れたのだと思います。
創業以来、どんなことを大切にして経営されてきたのでしょうか。
働いている人たちに良いキャリアを積んでほしいと、一貫して考えてきました。当社のミッションは「ミライの『はたらく』を、明るくする」。そう宣言する以上、まずは自社の従業員に「ライトワークスで働いて良かった」と感じてもらいたい。特に新卒で入社してくる人に対しての責任は重大です。彼・彼女らの「働くイメージ」はここで決まります。上場企業にとって株主が第一という考え方もあるでしょう。しかし、私は従業員のことを優先して考えます。それが最終的には株主のためにもなるはずです。

人事や人材開発部門の頼れる相談相手に
ミッションの話が出ましたが、併せて「不確実性が増す現代社会に必要な人材開発プラットフォームを提供する」というヴィジョンも策定されています。ミッション、ヴィジョンにはどのような思いが込められているのでしょうか。
大学院で労働経済を勉強していた頃から、日本の働き方は大きく変わっていくだろうと思っていました。
日本的雇用の特徴のひとつとして、終身雇用がよく挙げられます。しかし、これは戦後の高度成長期につくられた働き方でしかありません。当時は欧米の後追いで十分成長できたので、ビジネスモデルに悩む必要はありませんでした。そこで優秀な新卒を集めて社内で育てる長期雇用、いわゆる終身雇用が成立したわけです。
しかし、現在は他社の模倣で成功することは難しく、イノベーションが不可欠の時代です。新卒を社内で育てるだけの従来のやり方では対応できません。最近では「リスキリング」などの話もよく聞きますが、これもピントがずれているように感じます。ITスキルが足りない中高年を対象にリスキリングしても、AI時代に戦力になるとは考えられないからです。
とはいえ、アメリカ式のジョブ型雇用で全員が幸せになれるとも思いません。アメリカも雇用に関してさまざまな問題を抱えています。雇用と教育を結びつけた、新しい日本型モデルをつくることが必要です。業種・業態によっては微調整すべきですが、基本的には一定の長期雇用を確保しつつ、個人に成長機会を与えて、世界と同じレベルで戦える組織にしていくことが必要です。
そこでもっとも重要になるのが人材開発です。ライトワークスが一貫して取り組んできたのが働き方の変化に対応できる人材開発をICTでサポートする仕事でした。私たちのスタンスを集約し、言語化したものが当社のミッション・ヴィジョンです。
多くの大企業が貴社の「CAREERSHIP」を導入されている背景には、そうした課題意識の共有もありそうですね。
大企業ほど課題を感じていると思います。当社は株式市場でシステムの会社に分類されますが、顧客である企業の人事や人材開発部門からは「働き方や人材育成など人事課題の相談相手」と捉えてもらっています。
企業の人材開発は、コンテンツを並べた学習サイトを構築しただけで成果が出るような簡単なものではありません。従業員が積極的に自律学習している企業では、人材開発部門が今すぐ仕事に役立つコンテンツを大量に開発して提供しています。明日の仕事に必要な学習、必要に迫られてやる勉強がいちばん効果的なのです。あるいは従業員に次に目指すべきキャリアを示して、そのために何が必要かを具体的に示すとやる気に直結します。
雇用と教育を関連づける日本型モデルにはそういった要素も不可欠でしょう。当社ではこうした知見を提供する人材開発コンサルティングも多数手がけています。LMSはコンサルで明確になった課題を解決するためのツールと位置づけています。人材開発領域でのDXこそ、当社が提供している価値だと思っています。
興味を持って仕事に取り組む人が伸びる
現在の日本企業の「人と組織」「人事」に関する現状・課題をどう捉えていらっしゃいますか。
現在は二つの意味で歴史的な転換点だと思っています。一つは、経済環境の変化で長期雇用が成立しなくなってきたこと。しかし、いきなりアメリカ式のジョブ型にできるかというと、法制度の関係もあって難しい。日本型の新しい雇用モデルの形成が求められています。
もう一つは、人手不足。優秀な人材が足りないのではなく、労働力の絶対量が足りていません。少子化で若年人口が減っていることに加えて、働き方改革で労働時間の短縮も進んでいます。つまり「一人あたりの労働供給量」がこれからさらに減少していくわけです。しかし、先進国など豊かな社会では、人があまり働かなくなっても、お金はあるので消費は減らない、という現象が起きます。消費やサービスを支えるには頭脳だけでなく、人手も必要です。それが今の人手不足の本質でしょう。
しかし、残念ながらこの変化に意識が追いついてない経営者がほとんどです。これまでずっと、労働市場では買い手市場が続いていたからです。特に多くの人口を養える稲作が盛んだったアジア圏では、人手が余って仕事が足りないのがあたりまえでした。しかし、今後は海外も同じく人手不足なので、外国人労働者に頼るのは現実的ではありません。
こうした状況に企業はどう対応していけばいいのでしょうか。
生産性向上しかありません。効率的な仕事のやり方、人手をかけなくても結果を出せる組織のあり方を工夫することです。個人においては人的資本の蓄積でしょう。スキルアップすればできる仕事の幅も広がり、時間あたりの仕事量も増やせます。そうなるためには、自分への投資として勉強することが欠かせません。勉強の時間を生み出すために、効率的に働くことがますます求められています。
今後はどういった事業を伸ばしていきたいとお考えでしょうか。
顧客の課題解決に徹底してコミットしていきます。課題解決のために「こういうシステムの使い方があります」と提案していくことです。それができる人材育成にも注力しています。現在コンサルティングを担当するスタッフは、提携する大手コンサルティングファームの人事パーソン育成コンテンツを使って、今日の人事課題とは何か、どんな解決策が有効なのかといったことを学んでいます。人事的な発想ができるスタッフがコンサルティングすることで、よりいっそう顧客に寄り添える存在になっていきたいと考えています。
最後に、人材サービス業界、HRソリューション業界で働く皆さんに、ビジネスで成功するためのヒントや早い段階からやっておいたほうがいいことなど、アドバイスをお願いします。
興味を持って仕事に取り組む人は伸びます。HRはとても面白い分野なので、まず興味を持ってほしいですね。興味が違う分野にあるのなら、フィールドを移すのも一つの考え方です。私は東大を卒業後に官僚になり、留学させてもらうなど、最初は誰もが安定していると考えるキャリアでした。しかし、本当に興味があることは何かと考えた結果、ベンチャーや起業の世界に飛び込みました。当時は親もあきれていましたが、間違っていたとは思いません。自分が興味のあることをやるのがいちばんでしょう。
会社を立ち上げてから、出資企業の複雑な力学に翻弄(ほんろう)されて苦労することは多々ありました。そんなときも、どうすればライトワークスのためになるのか、自分たちの目指す仕事ができるのかといったことを考えて動いてきました。仕事をしていれば必ず疑問や新たな関心が生まれます。そこを自分で深掘りしていくことが大切です。「嫌だな」「大変だな」だけでなく、面白いと思って取り組んだことで、そこから得た経験や知識はのちのちの会社運営にも大いに役立ちました。興味を持っていたから頑張れたのだと思います。

(取材:2024年3月15日)
| 社名 | 株式会社ライトワークス |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア |
| 事業内容 | 次世代型学習管理・人材開発プラットフォーム、及び付帯するコンサルティングサービスの提供 |
| 設立 | 2001年7月 |